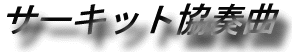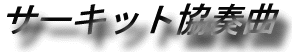第一章 二重奏
1987年、桜の花が過ぎ、表参道のけやきが若葉色に包まれる頃、
その物語は始まった・・・。
外は雨・・・・・。
綺麗なモカ・ブラウンに塗られたホンダ・S600のバケットシートに納まった霞は、手慣れた動作でイグニッションキーを回す。
カチカチと鼓動を始めた電磁ポンプの音が静まるのを待って、エンジンをスタートさせる。アクセルを半分程踏み込んだところで、小気味よい吹け上がりの音とともに、DOHC600ccのまるで精密機械の様なエンジンは眠りから目覚める。
ホンダミュージック!とまで呼ばれたその美しい排気音は、20数年の時を経た今でも力強いビブラートを響かせている。
雨に濡れた乃木神社前の坂道を、セカンドギアで駆け上がると、防衛庁前の大通りに出る。時計の針は9時30分を指している。
朝の六本木は比較的静か・・・、とは言うものの、車の流れは切れ間なく続いている。
秋山 霞、35才。 ヘア・デザイナー。
地方都市<秋田>に3店舗、二十数名のスタッフを抱える美容室オーナーであるとともに、乃木坂の高級マンションにプライベートのスタジオを持ち、ファッション雑誌やCFの為の創作活動を精力的にこなしている。
メルセデス、BMW、ポルシェ、等の高価な外国車が不法駐車をしている脇を、霞の小さなS600は、甲高い排気音を残してすり抜けて行く。
まだ暖まっていないエンジンをかばうように、レブカウンターの針を5000回転迄に抑え、丁寧なクラッチワークで、水温と油温の上がるのを待つ・・・・。
六本木交差点の信号で止まると、右となりの車線にオリーブグリーンの古いジャガーXJ6が寄ってくる。
髪に白いものが混じってはいるが、人懐っこい瞳と陽焼けした肌の、初老の紳士が話し掛ける。
「何年型ですか?」
「40年型です。」
「良い、なかなか良いですよ、あなたにとても良く似合っています。」
「ありがとうございます、私もジャガーがとても好きです、特にヒップラインが大好きです。」
霞は、悪戯盛りの幼子の様な笑顔を返している自分自身が照れ臭く感じる。
「おや、分りますか、私もこいつのこの丸みが好きなんです・・・・。」
「とても良くお似合いですね・・・」
「ありがとう・・・、それじゃ、気を付けて・・・・。」
「ええ・・・。」
ノンシンクロの一速に巧くシフトした霞は、左脇の二輪車を気にしながら左折する。
身長160cm、どちらかと言えば痩せ形の霞ではあるが、しなやかに伸びた手足は思ったよりも力強い運転をする。
霞が関のインターから首都高速に入る。
<首都高速・・・、私の東京の入口、そして出口・・・・。>
池袋のサンシャインビルを右に見てどこまでも進むとやがて首都高速の出口へと導かれる。続く新大宮バイパスは、走行車両が多い上に平均速度が速く、超軽量級のS600には辛いルートである。
大型トラック等に囲まれながらの走行に疲れを感じ始めた頃、ESSOの看板が目に止まる。
ウィンカーを出してそのスタンドに乗り入れると、案の定、働いている男達や客達の視線が容赦なく浴びせられる。
「いらっしゃい!・・・・、綺麗な車ですね・・・、何年型ですか?」
「40年、でもボディの大半は61年型ですけど・・・。」
「レストア車ですね!。 いいなあ・・・・。」
「ありがとう、ところで有鉛ガソリン置いてますか?」
「一寸待って下さい、別タンクに寄せたのがあった筈です・・・。」
首都高速を降りた頃から小降りになっていた雨が、もうすっかり止んでいる。
ローヒールのパンプスを履いているとはいえ、レーシングカー並の低いトライビング・ポジションから外へ出るのは、一寸ばかりコツがいる。
普段は、<ギャルソン>や、<Y’s>のゆったりした長めのスカートが多い霞なのだが、この車で遠出をする時は、裾がレバーなどにひっかからないように、膝小僧が見える<ソニア・リキエル>のミニのワンピースを愛用している。
霞の自慢の脚線美に目を奪われながら、先程の若いスタッフが戻ってきた。
「どの位はいりそうですか?」
「たぶん20リットル位だと思うけど・・・。」
「あぁ、その位なら大丈夫です。 古いポルシェ・・・・・、ほら、サゴロとか言うの!あれに乗っているお客さんがいるんで寄せておいたんです。20リットル位ならお分けできますよ。」
「ありがとう、助かるわ・・・。ついでにOILも診てもらおうかしら、たぶん0.5リットル位入ると思うの・・・。」
「OK、むこうでゆっくりしてて下さい。」
スタンドの建物の中に入った霞は、思い出したように雑誌社に電話を入れる。
「もしもし、FPジャパンですか、秋山霞ですけど草野編集長はいらっしゃいますか?」
「あっ、霞先生ですね、おはようございます、少々お待ち下さい。」
少し時間があって、いつもの力強い声で草野が出た。
「はい、もしもし霞さん、昨日はどうもお疲れ様。」
「いいえ、こちらこそお世話になりました。」
「昨日の写真ね、丁度今 ネガを観ているところなんですが・・・、なかなか良いですよ、二点目の作品が特に良いみたい・・・、力が抜けていて、とっても綺麗に上がっていますよ。」
「ありがとうございます、編集長にそうおっしゃって頂けると本当に心強いです。おかげで安心して帰れます。」
「あっ、今どちらからですか?」
「大宮バイパスのスタンドからなんです。」
「そうですか、じゃ今日もまた、例の車ですね。」
「ええ。」
「いいですねえ・・・、ところで、2・3日中にネガを送りますから、いつものようにセレクトお願いします。 今回はカラーページのメインで使わしてもらいますよ・・・。」
「ありがとうございます。」
「それじゃ、とにかく気を付けて・・・、また来月もよろしくお願いします。」
「はい、かしこまりました。 では・・・。」
丁度霞が受話器を置いたところへ、先程の若い店員が駆け寄ってきた。
「オイル、0.5リットル、ドンピシャリ・・・。よく分かりましたね。」
「ながーい付き合いですもの・・・。」
「そうか、長い付き合いですか・・・。 ともかく、お気を付けて・・・。」
「ありがとう。」
手早く精算を済ますと、再び街道の流れの中に身を任せる。
<ながーい付き合い・・・か。 もう何年になるのかしら・・・>
大宮市街の標識を過ぎると、東北自動車道のグリーンの案内板が目に付くようになる。
標識に従って進むと、間もなく岩槻のインターチェンジに着く。
ゲートへ続くカーブを抜けると、もう一度各メーターをチェックする。
「さあ、行くわよ!」
霞は、心の中でこう呼び掛けると、車をスタートさせる。
あっという間に4速、110kmに達する、レブカウンターの針は6500回転を指している。
<もう止めておきましょうね、これ以上は・・・。>
心の中でこうつぶやくと、左手をステアリングから離し、小刻みに震えている小さなシフトレバーにそっと触れてみる。
ミッションからダイレクトに突き出たシフトレバーは、エンジンの振動を正確に伝えてくれる。
霞の前に車はいない。
時折後ろから追い付く車の中には、からかい半分に、しばらく並走した後で下品な排気音を残して飛び去っていく高価なスポーツカーなどもいた。
一時間程走ったところで、上河内のサービスエリアのパーキングに車を止める。
雨もすっかり上がり、路面も乾いている。
<ここからはオープンで行こう・・・。>
そう決めた霞は、トランクからダウンジャケットを引っ張り出すと、そのまま上に着込んで大きめのボタンを止める。
体の線は細いが、決して小さくはない二つの胸の膨らみは、ダウンジャケット越しに形のよい曲線を描いている。
フックをはずし、幌を畳もうとしていると、背後から声がする。
 「お手伝いしましょうか?」 「お手伝いしましょうか?」
声のほうに振り向くと、初老の男が立っていた。
「いいえ、大丈夫です、慣れていますから・・・。」
そう答えて相手の男に微笑みを返した瞬間。
「あっ、あなたは・・・。」
「思い出してくれましたね、先程は失礼・・・。」
男は、今朝六本木の交差点で会ったジャガーの紳士であった。
「いえ、こちらこそ、それよりもこんな所で・・・」
「こんな所は無いでしょう。 追いかけてきたんですよ、貴女、いや貴女たちを・・。」
「本当ですか?、確かあれは六本木の・・・。」
「そう、アマンドの交差点でした。 私は広尾に住んでいるので、よく通るんですよ、あそこは・・・。」
「でも、なんでまた私のことを?」
「気になったんですよ、 妙に、 と言ったら失礼かな。 とにかく貴女の車のことが気になりましてね。 部屋に帰ってからも落ち着かなくて、とうとうここまで来てしまいました。 幸いナンバーが秋田だったのを覚えていたものですから、きっとここを通るだろうと思い、先回りをしてここで待っていたと言うわけです。」
「そうでしたの・・・。」
「とにかく、もう一度だけお目にかかりたかったのです。年寄りの冷や水と言うんでしょうか。」
「美人が駆る、モカブラウンのホンダスポーツ・・・。 うん、絵になっている、実に
良い!。」
「そうでしょうか。」
「そうとも、そうに決まっている。 こんなに条件の揃ったのは滅多に無い。 先ず第一に、ホンダスポーツは、圧倒的に赤が多い。次に白、そして黄色なんですよ。
モカブラウンのホンダスポーツなんて初めて見ましたよ。 そして、とにかく美人でなくてはいけないんです、この車に乗る女性は・・・。」
「まあ、随分お詳しいんですね。」
「特に、このS600が好きでしてね・・・。」
「同感、私もこのS600で3台目なんです。」
「とにかく、もしご迷惑でなかったら少し一緒に走らせて頂けませんか?。 あっ、私、沢木と申します。」
「秋山霞です、私こそ独り旅でさみしかった所なんです。 でも、ジャガーはスピードの出る車なのに、私たちの様な、ノロノロドライブに付き合わされたんじゃ、可哀想ですわね。」
「いやいや、とにかく楽しい、じつに愉快だ。」
「それでは行きましょうか?。」
モカブラウンのS600とオリーブグリーンのXJ6が、連なって新緑のハイウェイを走り出す。
オープンエアのツーリングは、時速110kmと言えどもかなりの風を巻き込むが、サイドウインドウを上げているのと、強力なヒーターのせいで霞の体は寒さを感じない。
後ろのXJ6は、着かず離れず適度な車間距離をおいて静かに着いてくる。
霞は思わずバックミラー越しにウィンクをする。
と・・・、先の電光表示板に灯りが点滅している。
ーーー5km先、事故発生、走行注意!ーーー
<事故だわ・・・!>
思わず、十数年前の、あの事故の時のことが霞の脳裏をかすめる。

・・その日・・・、
霞の意識が戻ったのは、救急病院のベッドの上であった。
<痛い!、体中の神経に針を刺されたような痛みが走る。>
「目が覚めましたか、もう大丈夫よ、何も心配要らないから・・・。」
「・・・ここは何処?・・・」
「柏総合病院という救急病院よ、私は付き添いの者です。 貴女は3時間程前ここに運ばれて来たのよ、危なかったわねぇ!。でもたいした怪我じゃなくって良かったわねー。」
「私、事故を起こしたんですか?、誰か他に怪我は・・・?」
「大丈夫よ、他の人は何ともなかったそうよ、それに相手の車の方が一方的に悪かったんだそうよ。」
「そうですか・・・。」
急に涙が溢れて霞の美しい瞳を曇らせる。
二十一才の、まだ少年のようなあどけなささえ感じさせる霞。
知らない町の見知らぬ病院、たったひとりベッドに横たわっている心細さと、心の片隅に渦巻いていた言い様のない寂しさが、頭の中を駆け巡る。
「どうしました、痛みますか?」
優しい男の声であった。
「院長先生ですよ、秋山さん。」
「秋山・・・?」
「そう、秋山霞さん、貴女の名前です。大丈夫、事故のショックで一時的に記憶を失っているのです。心配しなくてもいい、もう少し眠りなさい。後でゆっくりお話をしましょう。今はとにかく眠ることですよ。」
催眠術のようなその言葉に、包まれるように深い眠りに落ちていく霞であった。
夢の中で霞は、自分自身の記憶が少しずつ蘇るのを感じる。
遠くに聞こえるサイレンの音。 重い瞼を開ける。 視界が異常に狭い。
目の前のステアリングが折れて歪んでいる。
暗く狭い視界の中で、ガラスが砕け散ってしまったメーターが見える。
(ーーー事故ったんだわ、ーーー)
(ガソリン、・・・ガソリンの匂いがする! 危ない! エンジンを止めなくては・・)
手探りでイグニッションキーを切る。
だが、もう既に若駒の様な軽やかな鼓動はそこに無かった。
(早く降りなくては・・・)
ドアを開けようとして右側を見ると、何も見えなくなる。 右手で瞼をこするとヌルヌ
ルとした感触があり、手の甲が赤黒く血に染まる。
目をこらすと、足元の地面がかすかに見える。
エメラルド色の液体がアスファルトの路面に標紋を描いて流れてゆく。
右足を外に引き出して、車から降りようと試みる。
「動かない方が良い、座っていなさい。」
ぼんやりと警察官の姿が見える。
誰かが霞の腕を支えている。
薄れた視界の中、徐行してゆく車の列。
(この人達、私を見ているわ・・・)
そんなことを感じながら気を失ってしまった。
数時間ではあったが、深い眠りから覚めた霞の体は、横になっている限りでは痛みは感じなかった。
「免許証はこれですね。 秋山霞さん、21才、本籍は秋田県。 お宅の方には地元の警察署から連絡をしてもらっておきました。 同乗者はいませんでしたね。」
「・・・・たぶん・・・。」
「刑事さん、まだはっきりと思い出せないのかもしれません、あまり無理をしないで下さいよ。」
横にいた院長が、調書を取りに来た刑事に促す。
「車、私の車はどうなりましたか?」
「双方ともかなりいきましたね、たぶん全損でしょう。 貴女がこの程度の怪我で済んだのが不思議なくらいひどい状態でした。」
「そうですか・・・。」
その日霞が失った車は、兄の形見のS600であった。
霞は、地元の女子高校をトップで卒業したあと、ヘアデザイナーを目指して東京の美容学校に入学した。
その頃、たった一人の兄、洋一は、早稲田大学理工学部の4年生であった。また、父を早く亡くした霞一家は、母一人の手で支えられており、努力家の母郁子は英語教師として短大の教務主任を勤めていた。
その春から、母一人を秋田に残して、霞は兄と同じように東京に住むことになったのである。
代々木上原にある女子寮に入った霞は、週末ごとに食料を買い込んで、兄のアパートへ掃除にでかけるのが楽しみの一つになっていた。
その頃の洋一は青梅街道沿いの質素なアパートに、中学時代からの親友田村と共同生活をしていた。
霞が上京して半年程たったある日、頂度、代々木の森が秋色に変わって間もない頃であった。
突然、洋一が霞の寮に訪ねてきた。
「どうしたの? 兄さん。」
「突然で悪かったな霞、じつは頼みがあるんだ。 おまえの寮の庭に、この車を預かってくれないか?。」
それは、洋一が大切に使っていたレモンイエローのホンダS600であった。
車が唯一の趣味とも言える洋一が、家庭教師のアルバイトをして買ったというその車は、年式こそかなり古いが、機械に詳しい洋一が手を入れていただけあって、非常に程度の良いものであった。
「実は、田村の奴がセクトの対立で<全赤連>に狙われているらしいんだ。あいつ近頃随分と運動に夢中だったから・・・。」
「全赤連・・・って、お兄ちゃん、危ない事しちゃ嫌よ!」
「大丈夫、心配しなくてもいいよ。ただ、田村の奴を放り出す訳にもいかないから・・・・・。 奴ら、最近警察にも追い詰められているから、無茶をやっているみたいなんだ。
大事な車に悪戯をされないように、霞のところに非難したい、という訳。」
「そう・・、車のほうは寮母さんに頼んでみるからいいけど、霞、兄さんの方が心配だな
あ・・・。」
「ねぇ、約束して! 絶対に無茶な事をしないって・・・。でないと母さんに・・・。」
「後は言うな、霞! とにかく、おふくろさんには言うなよ。余計な心配をかけるだけだから・・・。」
「解ったわ、お兄ちゃんの言うとおりにするわ・・・。」
「それと、しばらくは俺たちのアパートには近づかない事! いいな!。」
そう言い残すと、くるりと背を向けて、足早に立ち去った洋一であった。
霞が洋一の元気な姿を見たのは、この時が最後であった。
十日後、全赤連が対立するセクトへの襲撃戦を展開し、洋一と親友の田村は早朝のアパートに、鉄パイプとヘルメットで武装したグループ数名に押し入られたのである。二人は応戦する間も無く、あえなく叩き潰されてしまった。運び込まれた救急病院に霞が駆け付けた時には、もう既に二人とも息は無かった。
荻窪にあるその病院の遺体安置室で、線香の煙に包まれた小さな祭壇の前に座り、霞は放心状態のまま、母の来るのをただひたすら待っていた。

昨夜来の雨が若葉の緑をなお一層爽やかに磨き上げる。
やまあいを縫うように走る、霞と沢木の二台のビンテージカー。
本当に走ることの術を知っている者たちの優しいデュエットがどこまでも続く・・・。
那須高原SAの標識が目に留まった時、霞のS600のバックミラーに、XJ6のパッシングが届く。左手を真上に上げると親指を突き上げてOKのサインを送った霞は、左へウインカーを出して減速をする。
深夜のパーキングエリアと違い、長距離便の大型トラックが岩のように立ちはだかることもなく、ランチタイムとはいうものの比較的見通しの良いパーキングの中で、霞は容易に2台続きのスペースを捜し出した。
S600の右隣に停止したジャガーのサイドウインドーが静かに降りる。
「お疲れさま!」
「お疲れになりましたでしょう。」
「いや、久しぶりのツーリングでゴキゲンです。それはそうと、おなか空きませんか?」
「ペコペコ!、じつは朝食もまだだったんです・・・。」
「よし、決まった!、何か食べに行きましょう。」
手慣れた動作で、イグニッションキーを抜くとパッセンジャーシートの足下に置いてあったハンティングワールドのショルダーを、無造作に肩に掛けて霞は車から降りる。
「幌は上げなくていいんですか?秋山さん。」
「どうぞ霞と呼んで下さい、そのほうが気が楽ですから・・・。昔と違ってドライバーのマナーが良くなっているし、私、この車にいたずらされた事ないんです・・・。」
「そうですか・・・、いや、それほどこの車が可愛らしいという証拠ですね。」
「まあ! 変なところで感心なさらないで下さい・・・。」
こんな言葉を交わしながら、二人はレストランに向かった。
「今日はせっかくのツーリングなのに、私のような年寄りがお邪魔をしてしまい、申し訳ありませんでした。」
「とんでもありません、しっかりとエスコートして頂き、さっき走っている間中ずっと幸
せな気分でしたわ。」
「そうおっしゃって頂けるとうれしいです。お言葉に甘えて、もう少し一緒に走っても構いませんか?」
「もちろんですわ、沢木さんさえご迷惑でなかったら私ももっと一緒に走りたい・・・」
軽い食事の後、コーヒーを飲みながら、他愛のない会話を楽しむ二人であった。
親子程も年が違う二人ではあるが、オールドカーという共通言語をもった二人の回りには、居心地の良い空間が広がるのを霞は感じ始めていた。
「ところで、霞さんは今日中に秋田までお帰りの予定なのですか?」
「ええ、明朝からまた仕事が入っておりますので、遅くとも今晩中には戻ろうと思って居ります。」
「そうですか・・・、今はまだ一時ですから、いずれにしてもどこかで晩御飯を食べてもそれほど遅くはならないでしょう・・・。どこか美味しいものを食べさせてくれる処を知りませんか?、 どのみち私は明日の夕方まで東京に帰れれば構いませんから・・・。」
「そうですね、このまま行くと盛岡で6時過ぎる頃ですから・・・、そうだわ!とっても
素敵な所がありました、少し遠くても構いません?」
「平気!平気! どこですか?」
「私、とっても気に入っている所があるんです。あそこなら絶対気に入って頂けると思います・・・。田沢湖には、いらした事ありますか?」
「ええ、以前よく行きました。」
「湖畔に田沢湖プリンスホテルが出来たんです。出来たといっても以前からあったホテルをプリンスホテルが買い取って全面改装したんですけれど、とっても静かで素敵なホテルになったんです。今から急げばディナーに間に合うでしょうから、是非あそこが良いと思います。」
「よし決まり! 田沢湖まで行きましょう。 そうと決まったら、私は今晩そこに泊まる事にします。明日の朝発てば夕方までには東京に戻れるでしょう・・・。今夜はご機嫌なディナーになりそうですよ、これは良い・・・!」
二人とも、悪戯を企んだ子供達のような笑顔を見合わせて、思わず吹き出してしまう。
途中、給油の為の小休止はしたものの、ほとんど走り通しで田沢湖に向かう。
夕陽が山肌をなめるように照らし出す頃には仙岩峠に差し掛かる。
奥羽山脈のど真ん中に掘り抜かれたそのトンネルは、前半1000メートルは緩い上りで、後半の1000メートルは緩い下りになっている。
リアの、チェーンによる駆動システムを痛めないように、無理なエンジンブレーキを避けながら、長い峠道を走り抜けた霞のS600と相棒のXJ6は、やがて田沢湖町に差し掛かる。
冬になるとスキーをキャリアに満載したマイカーの列が出来るその道を、5分程走ると急に視界が広がり、湖畔に出る。
対岸のプリンスホテルまでは、右に行っても左に行っても、同じ10kmの道のりではあるが、霞は右に折れる事にする。 左ハンドルのジャガーに乗った沢木に夕陽に染まった湖が良く見えるように、北側の岸辺を走る事にしたのである。
田沢湖プリンスのパーキングに車を止めて降り立った時、湖畔は丁度、完全な陰に入り駒ケ岳の中腹から上だけが、夕陽に赤く焼かれていた。
やがて間も無く、藍色に変わりゆく夕空に深く沈んでゆく奥羽の山並みが、やや疲れを感じ始めていた霞の瞼に、優しく映し出されてゆく・・・・。
途中、電話で部屋をリザーブしておいた沢木は、フロントでチェックインだけを済ませてキーを受け取ると、まっすぐに霞とともにレストランに入る。
霞の選んだ席は、窓際の奥から三つ目のテーブルであった。この席から眺める田沢湖が一番美しい事を、霞はよく知っていた。
二人がテーブルに着いて間もなく、ホテルの支配人の原木が二人の席に近づいて来る。
「沢木先生、お久し振りです。チェックインの知らせがあったものですから、早速ご挨拶をと思いまして・・・・、お食事前に申し訳ありません。 おや、これはこれは、秋山様もご一緒でしたか・・・、気が付かなくて済みませんでした。 沢木先生と秋山様は以前からのお知り合いだつたんですか・・・?」
「まあ・・・そういう事です。 私の大切な友人なのですよ、霞さんは・・・ね!」
「ええ・・・、まあ・・・。」
何となく力のない返事を返した霞は、原木支配人がテーブルから離れるのを待って沢木に尋ねる。
「沢木さん、以前から御存じだったのですね、ここのホテルは・・・。」
「ええ、ここのホテルの改装工事の時に、設計を頼まれましてね・・・、いや、隠してい
た訳ではないのですが、霞さんがあんまりお気に入りだったものですから言い出しにくくて・・・・。」
「と、言いますと、沢木さんというのは、あの建築家の沢木先生ですの・・・?」
「ええ・・・」
「そんな・・・!、私、恥かしい・・・! 困ります、本当に困ります・・・。私とんで
もない図々しい事をしてしまいました。 本当に・・・・・。」
「お忙しい方なのに、こんな遠くまで連れ出してしまって、本当にゴメンナサイ・・。」
「とんでもない、私が勝手について来たのですから何も気になさる事はありません。」
霞が、恥かしさの為に顔を赤く染めた時、壁一面のガラス越しに映し出されていた山々が、月明かりの夜空にすっかり溶け込み、対岸の明りだけが湖面を美しく浮き立たせていた。
「綺麗!・・・、何もかも・・・・。」
思ってもみなかった出会いに、少女のようなときめきを感じた霞であった。

その晩、霞が秋田市を一望出来る山の上にある自分の部屋に戻ったのは、十時を少し過ぎた頃であった。 いつになく高ぶっている心を静めようとしてバドワイザーの栓を抜いてはみたものの、なかなか興奮の波は引いてくれそうもない。
熱いシャワーを浴び、下着を何もつけないで洗いざらしのリーバイスに足を通す。
ビル・エバンスのLPに針を置き、2本目のバドワイザーを抜く頃になって、ようやく緊張の糸から解き放されるように落ち着きを取り戻したのであった。
モデルの笑顔とストロボの閃光、そして小気味よいシャッターの音が響き渡るスタジオでの仕事。
草野編集長の元気な声・・・。
雨に洗われた朝の乃木坂・・。
オリーブグリーンのジャガー・・・。
サ・ワ・キ・先生・・・・。
ほんの数時間前、食事の後のエスプレッソを静かに飲み終えた霞の前に置かれた名刺には、<沢木明人建築研究所・代表・沢木明人>と小さく刷られていた。
日本を代表する建築家と言っても過言ではないその初老の男は、信じられないくらい無邪気な瞳と心を持っていた。
食事を終えて車に戻る霞・・・、そしてそれを寂し気に見送る沢木・・・。
「とうとうお別れですね・・・・。」
「沢木先生、本当に遠くまでありがとうございました。 おかげでとっても幸せな一日でした。」
「こちらこそ、もし宜しかったら、是非又一緒に走りましょう。」
「ええ、楽しみにしています・・・。」
「今度東京にいらした時は、必ずお電話下さい、待っています。きっとですよ・・・。」
こうして別れた沢木のことを考えながら、うとうとと眠りの中に引き込まれていく霞であった。
翌朝、普段よりも少し早く目覚めた霞は、ゆっくりとバスに浸かり、自慢の長い髪に丁寧にシャンプーとコンディショナーを使ったあと、荒めのコームでとかし、ウェーブを整える。
自然乾燥の出来るロングのウェーブヘアーを垂らしながら、冷蔵庫から野菜ジュースのミニ缶を取り出して、一気に飲み干す。
毎日の朝シャンと野菜ジュースの習慣は、15年前、アメリカで勉強していた頃から変わっていない・・・。
簡単なメークを済ませた後で時計を確認した霞は、受話器を持ってアルフレックスのソファーにゆっくりと腰を降ろし、田沢湖プリンスホテルの沢木の部屋に電話を入れる。
「はい、沢木です。」
昨夜、さみしそうな顔でパーキングまで送ってくれた沢木の事が思い出されて、急に懐かしさが込み上げてくる霞であった。
「おはようございます、霞です。」
「ああ、霞さん、昨夜はどうも・・・。」
「田沢湖の朝はいかがでした?良くお休みになれましたか?・・・」
「ええ、相変らず、今朝の湖も素晴らしい眺めですよ・・・。本当にこの湖は秋田県の最高の財産ですね・・・。」
「ええ・・・。」
「霞さんのおかげで素晴らしい朝を迎えました、本当にありがとう・・・。」
「とんでもありません・・・。」
「ところで、霞さんの東京のスタジオは乃木坂でしたね。」
「ええ、乃木神社のすぐ横にあるマンションの中にあります。」
「そうでしたね、私の研究所は表参道ですから今度是非寄って下さい。あなたに何かお礼をしなくては・・・。」
「お礼だなんて・・・、それよりも私、先生の大ファンなんです、もしご迷惑でなかった
ら本当にお邪魔していいでしょうか?」
「もちろんです、ここひと月くらいは、海外に出る予定はないので、いつでもいらっしゃい。きっとですよ・・・。」
つづく・・・
目次へ戻る
次の章へ
|