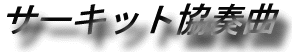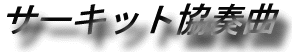|
第二章 F−1放映推進委員会
「はい、それでは先生もお気を付けて・・・。」
そっと受話器を置いた霞は、再び訪れた小さな心の高まりを感じながら、通勤用に使っているS600クーペのバケットシートに体を沈める。
霞のガレージには、モカブラウンのS600オープンボディと、シルバーメタリックのS600クーペの二台が仲良く並んでいた。 年式はそれぞれ40年式42年式だが、どちらもしっかりと整備が行き届いていた。
もっぱら通勤に使うことの多いクーペのほうはキャブのセッティングを始め、ショックも柔らかめの、扱いやすさを基本に仕上げられていた。
三日ぶりにサロンに出た霞をいちばん待ち焦がれていたのは、もうじき技術者になろうとしていたマリであった。
「先生、私死にそう・・・。」
いまにも泣き出しそうな顔で霞の前に表われたのであった。
「まあ、どうしたの・・・?」
「先生がお帰りになる迄に、ウェッジのパターンを合格しているように言われていたんです・・・。」
「そうよ、あれが合格したら、次は私が技術者の試験をする事になっていたのよね。」
「そうなんです、でもどうしてもサイドのつながりが悪くて原先輩のOKが貰えないんです。ああ・・・、私って素質がないんでしょうか。 私、もう死にそうです・・・。」
「マリさん、このパターンに取り掛かってどのくらいになるんだっけ?」
「もうじき3週間になります。」
丁度そこへトレーニングの指導係の原が通りかかる。
「原君、ちょっと・・・。」
「おはようございます、どうしました?」
「じつはマリさんが死にそうなのよ・・・。」
「ウェッジの件でしょ・・・。」
「そうなの、きっとシェープが荒いんだと思うけど、もう一度見てあげてくれないかな・・・。」
「ハイ、かしこまりました、結構いい線いってるんですが、なにせおっちょこちょいなもんですから、調子に乗るとすぐシェープが雑になるんですよ・・・。」
「じゃあ、もうひと踏ん張り、そのおっちょこちょいの面倒を見てあげてくれる・・?」
「原先輩!肩を揉みましょうか・・・?」
「おまえはな、いつも死ぬ死ぬって大騒ぎをするんだから、この前のボブのパターンのときだって・・・・。」
「マリさん、大丈夫よ、原さんだってウェッジの時に、ひと月半はかかったんだから・・・・・。」
「あっ、先生それは言わない事に・・・・。」
「あっ、そうだった、ごめんなさい。いえ、それだけしっかり納得する迄勉強したという事を言いたかった訳なのよ・・・・。」
「ああ、そうだったんですか。じゃあ、私も原先輩にあやかって、もう一月くらい・・・・・。」
「そんな遠慮しなくたって、いっそ三か月くらい頑張ってウェッジの神様というのも悪くないんじゃないかな・・・。」
「そんなー、原先輩、助けて下さい・・・。何なら今日のお弁当も・・・。」
「コーラもつけるかい?・・・」
「馬鹿らしい!・・・。とにかく頑張ってね。」
「はい、かしこまりました。」
そんな騒ぎを聞き付けてマネージャーの結城美穂が事務室から出て来る。
「あっ先生、おはようございます。 撮影のほうはいかがでしたか? 今回はヘルプをお連れにならなかったので心配していたんです。」
「ええ、大丈夫だったわ、モデルもいい子だったし・・・。」
「ああ、そういえばモデルクラブのフォリオから電話がありました。今回のモデルのクリスティが一昨日の作品が上がったら、是非、自分のコンポジットに使わせて欲しいと言っているらしいんですが、雑誌社さえ良ければ構わないといつものように電話番号を教えておきました。」
「そう、良かったわ・・・。」
「それから、昨夜東章産業から電話がありました。お帰りになったら電話をくださいとのことでした。」
「了解!」
「それともう一つ、良いお知らせ・・・。」
「解った、ポチが見つかった・・・。」
「残念でした、ポチの事はもう諦めてください、だいいち迷い猫だからってポチなんて名前を付けるんだから、きっと嫌になって愛想を尽かしたのかもしれませんよ・・・。」
「そうかしら・・・、きっと気に入ると思ったんだけどなぁ・・・。」
「そんな事じゃなくって、もっと大きな事。 実は昨日、藤盛特許事務所の先生から連絡がありまして、ヴェールパームの特許、アメリカが許可される事になりそうなんだそうです、それで多分他の国のもほとんどがOKになるだろうから、大変な事だっておっしゃってました。」
「えっ、本当! 取れたのね・・・!」
「おめでとうございます・・・。」
「これで私たちのオリジナルのテクニックが世界に認めて貰えるのね・・・。」
「またお忙しくなりますね・・・。」
朝礼の後、霞は指名のお客を五名ほど、たてつづけにカットして、ようやく事務室に入り、受話器を持ったのは、お昼少し前の事であった。
「もしもし、東章産業ですか? 秋山ですけれど、博士はいますか?」
「ああ、霞先生、お帰りになられたんですね、少々お待ちください。」
少し間があって、霞が絶対の信頼を寄せている整備工場の社長吉田が出る。
霞が博士と呼ぶのは単なるニックネームではなく、本当に工学博士の博士号をもつ彼に対する、尊敬の証明なのであった。
「もしもし、霞さん、いつ戻ったんですか?」
「昨夜遅く。」
「エンジンのほうはどうでしたか?、ちょっと気になるところがあったんだけど。」
「悪くはなかったみたい、でも博士が言ってたように、オイルの減りが激しくなってきたし、5500回転あたりの共振音がますます大きくなってきた事は確か。」
「やっぱりそうだろうな・・・。実はホンダ部品から連絡が入り、ピストンとリングが届いたそうなんですよ、それで、ぼちぼちエンジンを開こうかと思うんですよ。」
「是非お願いします、これでいよいよ心臓も若返るんですね。」
「真面目にやれば二日もあれば事足りるんだけど、特にうるさい誰かさんの車なので、出来ればいつものように、晩飯を食ってからじっくりやろうと思っているので、余裕をみて一週間ほど入院させて下さい。」
「分かりました、じゃあ今晩にでも持っていきますからお願いします。」
「ああ、それから、もし今晩来てくれるんならうちの客の連中が、是非霞さんに頼みたい事があるそうなんで、呼んでおいて良いですか?。」
「じゃあ九時に行きます。」
「じゃあ・・・。」
その日、終礼を終えて自分の部屋に戻ったのは八時を少し回っていた。
いつものように熱いシャワーを浴び、腕や首に付着した小さな毛くずを洗い落した後で当然の事のように何も着けない小さなお尻を、今日はVery
Slimのストーンウォッシュのジーンズで更に締め付ける。
食事をしている時間はないので、ヨックモックを一枚口に放り込むと、冷蔵庫から良く冷えたアップルタイザーの瓶をとりして一気に飲み干す・・・。
「ウー、シュッパイ・・・。」
こんな事を口走りながら、真っ赤なブルゾンを手に持つと、足早にガレージに戻る。
通勤に使ったクーペの方は、まだ排気の匂いに包まれている。
今度は昨日まで楽しい時を付き合ってくれた、オープンボディのS600のバケットシートにそのジーンズの小さなお尻を沈める。
真紅のブルゾンにも、そしてその胸元に見えかくれしている真っ白なTシャツにも綺麗な刺繍で、霞のサロン<ウェーブカンパニー>のロゴが描かれている。
お客様にプレゼントする為に、霞みずからデザインして作らせた特注品である。
ポルシェやフェラーリが無造作に並んでいるその工場の中の空いているスペースに、霞がS600を滑り込ませたのは、約束の時間の5分前であった。
「こんばんわ。」
「いらっしゃい、待っていました・・・。」
質素な応接椅子と大きな灰皿があるその工場の、事務所兼応接室には、既に5人の男たちが話に花を咲かせていた。灰皿の中の吸い殻の量と、室の中にたち込める煙の様子からすれば、かなり話は盛り上がっていた様子である。
どの顔も霞にとっては馴染の深い、無邪気な仲間たちであった。
つい最近ローバーから赤いフェラーリに乗り換えたドクター白井。
三か月前に、純白のポルシェターボで信号機に激突して大破、くの字に折れ曲がったボディから、エンジンが千切れて飛び出したという程の事故を起して、みんなを心配させたばかりの河村君。
ブティックのオーナーの村田。そして新聞記者の白石と博士の五人である。
「じつは・・・・。」
話を始めたのは河村であった。
「霞さん、今年フジテレビが5年契約でF−1グランプリの放映権を買った事は知っているでしょ。」
「ええ。」
「それでフジテレビの系列局がテレビ秋田だという事も知っていますね。」
「もちろん!」
「とすると本来なら今年はテレビ秋田でF−1が見れる事になりますよね。」
「違うんですか?」
「まさかと思うんですが、今日、局のアルバイトをしている友達から聞いたんです。秋田はモータースポーツなんかでスポンサーが集まる訳ないっていう事で、オンエアしない事に決まったんだそうです。許せないっすよねー!」
「初耳だわ、今年は中島も走るし、セナもロータスでホンダエンジンだから、きっと面白くなりそうなのに・・・。」
「でしょう・・・。」
「そこで僕達の少ない知恵を絞って出した結論が、この際、霞さんに一枚、服を脱いで貰おうと・・・。」
「馬鹿!服じゃ無くて肌だよ肌。」
「おっといけない・・・。つい本心が・・・。」
「全く河村はデリカシーというもんが欠如してるんだから・・・。」
「解ったわ、テレビ秋田と交渉すれば良いんですね・・・。」
「出来ますか?・・・」
「聞いてみないと何とも言えないけど、秋田だけF−1が観れないなんて、絶対悔しいわよね。」
「それで、さっきから皆で相談をしていたところなんだけど・・・。」
「この際、必要とあらば、皆でスポンサー集めをしようかと思うんです。」
「となると、局の方からも何が何でも良い条件を出して貰わなければならないし・・。」
「そのためにはテレビ秋田の大口スポンサーである、ウェーブカンパニーの秋山霞先生の一声が是非とも欲しい・・・、という訳なんです。」
「了解。」
霞は、手に持っていたセカンドバッグから、黒い革のカバーに包まれたアドレス帳を取り出すと、そばにあった受話器に手を延ばす。
「もしもし、相田さんのお宅ですか?。夜分申し訳ありません。ウェーブカンパニーの秋山ですが、ご主人はいらっしゃいますか?。」
「ああ、秋山先生、いつも主人がお世話になっております。少々お待ち下さい、丁度今帰ってきたところです・・・。」
ひと呼吸おいて、テレビ秋田の営業部長の相田が出る。
「もしもし、霞先生ですか、どうもいつも・・・・。」
「夜分ごめんなさい、この間の秋田酒造の坂井さんの奥様、相田さんにとっても良くして頂いたとお礼を言ってました。どうもありがとうございました。」
「いやいや、こちらこそ、御客様を紹介して頂いたのですから・・・、霞先生の顔をつぶさないように心してやりますので、今後とも・・・・。うちの常務も宜しくといっていました。」
「ところで、今、急いで電話をした件ですけれど・・・。一つ、相田さんのお力をお借りしたいんです。」
「何でしょう・・・。」
「じつはF−1グランプリの事なんです・・・。 秋田ではオンエアしないって本当ですか?」
「ああ、あれですね、一昨日の営業会議で問題にあがったんですが、いま、うちの会社の事業部でやっているクィーンズゴルフが控えているものですから、とてもモータースポーツの企画物でスポンサー探しには回っていられない。という事で、我が社では見送る事になったんです。」
「その話なんだけど、スポンサー集めも含めて協力しょうというグループがあるんだけれど、話に乗って頂けないかしら?」
「本当ですか?」
「本当です。実は、今そのグループの人達がここに揃っているんです。」
「それじゃあ電話では何ですから、すぐにこれから伺っても良いですか?。」
「そうして頂けると最高です・・・。」
ものの十五分程で霞たちの待つ事務所に現れた相田は、幾分赤味のさした顔で・・。
「申し訳ありません、ついさっきまで接待で川反にいたものですから、ちょっと酒が入っていますがご勘弁を・・・。」
「そんな事気にしないで下さい、無理言ったのはこちらですから・・・。」
霞の口からひととおりのメンバーの紹介を受けた後で・・・。
「ところでさっきの電話での話は本当ですか?」
「ええ、ただし条件にも寄りますけれど。」
「そう言っちゃあ何ですが、どうせ一度はボツになった企画ですから、もし、物になるんでしたらかなりの無理は通せると思います・・・。」
「肝心な所なんですが、金額はどの位の線を考えていたんですか?局の方では・・・?」
「キー局、つまりフジの方では、今回は特別企画なので最低でも120万くらいの番販価格を見込んでいたようなんです。それに120分のCM枠をBタイムで押えたとしても、最大取れたとして1分CM12本、10万×12本で120万。合わせて240万でいければ・・・と考えたのですが、とてもとても無理だ・・・となった訳です。」
「なるほど、Bタイムで1分24万はちょっときついわね・・・。」
「15秒CMのスポットで6万か・・・。」
五人の男どもは、先程までの威勢の良さが、跡形もなく消えてしまっていた。
「ちょっとしんどい企画でしょう・・・・、われわれも是非とも取りたかった番組なんですが、そこまではちょっとクライアントに言い出せない額だったものですから・・・。」
「相田部長、そこを何とか部長のお力で・・・・。」
「他ならぬ霞先生のお願いですから、私としても是非とも何とかしたいとは思いますが・・・。」
ドクター白井が、しびれを切らしたように口を開く。
「局の企業努力で、最大限いくらまで値切って買ってくるか?、まずそこからだなー。」
「そうですねー、昨日の昼に営業会議の結果を先方に伝えたときの感触だと、かなりがっかりしていた事は確かだから、もう一度交渉してみる価値はあるかもしれませんね。」
「ほう・・・。」
「いくらうまく話をしたとしても、半額というのはないでしょうから、まあ、80万位なら何とか頼めるかもしれません。これはあくまでも私の感ですが・・・。」
「もしそうして貰えたらいくらか可能性が出てくるかな・・・。」
「あとは、Bタイムの時間帯というのはどうだろうか・・・。」
「そうですよ、だいいちF−1の好きな連中は夜更しが多い筈だからいくら遅くても構わないと思うなー。」
「河村はすぐに自分を基準にして考えるんだから・・・・。」
「でも、今のはすごいアイデアかもしれないわ・・・。」
「相田部長! いっその事BタイムとかCタイムなんてけちな事は言わないで、全部の放送が終ってからテストパターンの代わりにF−1をオンエアする・・・、というのはどうなんでしょうか?」
「えーっ、そんなに遅くって良いんですか?」
「もちろん早い時間帯にこした事はないんでしょうけれど、最近はVTRも普及してきたし、夜が苦手な人は録画して翌日にゆっくりと見れば良いんだから、この際、どんな時間帯であってもオンエアする事が最大の目的だから・・・。」
「そうだとも、相田さん、今の霞先生のアイデアはいけるかもしれませんよ。他の番組をつぶす心配もないし、この収入はそっくり売り上げUPになるではないですか・・。」
「そうか、その方法がありましたね、それならば人件費も泊りの連中に特別手当を出して頼めば何とかなるし、電気代くらいのものだからたかが知れているし・・・、これなら格安にできますね。」
「よし決まり!それでは番販価格プラスαで手を打ってくれたまえ相田君・・・。あとは僕達が一肌脱ぐから、任せなさい・・・。」
「白井先生ったら、急に元気になるんだから・・・。」
「いやーっ実に楽しいね。 ・・・ナカジマ!・・・頑張れよー!。」
「やれやれ・・・」
皆がひとしきり大笑いをした後で、博士が話し出す・・・。
「これでこの計画は何とか見通しが付きそうだから・・・、そうと決まったら我々の会を作らなければいけないな・・・。」
「そうだ、何か良いグループ名を付けなくては・・・。」
「中年暴走族・・・・! 何て駄目だよな。」
「やはり、一般受けするのが良いよ。」
「F−1を見る会・・・じゃちょっと味気ないし・・・。」
「F−1友の会・・・。F−1後援会・・・。F−1を放映する会・・・。」
じっと考え込んでいた新聞記者の白石が、ふと顔を上げて。
「こんなのはどうでしょうかね、F−1放映推進委員会。」
「それいけるぜ!さすがブン屋だねー。」
「うん、素敵、何となく格調が高くて良い名前ですね。」
「よーし、決定!F−1放映推進委員会が、本日ここに発足いたしまーす。」
河村が声高らかに、宣誓する。
「それでは、このメンバーが発起人という事で、手分けをしてスポンサーを集める事にしよう・・・。」
「となると、会長は誰にしようか?。」
「この際、局との窓口になって貰わなければならないんだから、霞さんにお願いしたほうが良いと思うけれど、どうみんな?。」
ドクター白井が、自信を持って発言する。
「賛成!霞さんのおかげでF−1が観れる事になったんだから、大賛成!」
「えぇーっ! 責任重大だわ! でも、こうなったからには後には引けないので、せいぜい相田部長にご無理をお願いする事に決めました。どうぞ宜しくお願いします。」
一同拍手!
「こちらこそ・・・、一番手強い代表幹事ですよ、私どもにとっては・・・。」
「それと、事務局は博士にお願いして良いですね。どのみち我々は毎日のようにここに来て博士の機嫌をとっている事だし・・・。」
「あれが機嫌とりですかねー、ドクター。どう見ても暇潰しのようだけど・・・。」
「いいんですよ、ドクターのフェラーリに今度からスピードリミッターを組み込んでおきますから・・・。」
「いやっ、冗談、冗談、今度本当に機嫌とりしますからリミッターだけは勘弁・・・。ね博士・・・。」
一同、大爆笑・・・。
「F−1グランプリか・・・・。」
霞の頭の中に、半年程前の鈴鹿サーキットの思い出がよみがえる・・・・。

オープンボディのS600のレストアが終り、博士からそのアクセサリーのような七宝の装飾が施された、綺麗なキーを手渡されたその日・・・。モカブラウンのボディはしっかりと磨き込まれて、ひときわ輝いていた。
内装も、幌も、もちろんタイヤまで、全てピカピカの新品のそのスポーツカーは、メッキのバンパーやモール等が、幾分アンティックな感じを与えてはいるものの、その曲面の綺麗なボディシルエットは、まだまだ古さを感じさせない。それどころか、みんな同じようなデザインの最近の車たちの中にあって、ひときわ個性的な品のよいフォルムを持っていた。
「どうです・・・?。」
「うん、すっごくいいっ・・・・・!」
「でしょう・・・!、東章産業の、快心の作・・・・です。」
「さいわいボディパネルは、全部パーツがあったし、足回りも、よくこれだけ揃ったもんだと感心しましたよ。だいいち20年以上も前の車のパーツを未だに造ってくれるんだから、ホンダは一体何を考えているんでしょうね・・・・。この車で残っている所といえばフレームとエンジンだけですよ・・・本当に・・・・。」
「ああ、それから、そのエンジンだけど、そのうちパーツが揃い次第バッチリ組みますから期待していて下さい・・・。それ迄はレブリミットを7000回転で我慢していて下さい。」
「了解!」
十数年前に、千葉で事故ってスクラップにしてしまった、兄の形見のS600以来の、本当に久し振りに握ったその木製のステアリングは、やはり何とも言えない味わい深いものであった。
「うん、これならば行ける・・・・。」
「何処へ・・・ですか?」
「じつは、レストアが終る迄迷っていたんだけど、この九月に鈴鹿でホンダスポーツの走行会があるんです。」
「ああ、ツインカムクラブのミーティングでしょう・・・。」
「そう、あのミーティングに一度出てみたかったの・・・。」
「そうか、鈴鹿サーキットか・・・!」
「ねっ! 博士、この車なら大丈夫でしょ・・・・。」
「うっ、うん・・・・・・・。多分大丈夫だとは思うんだけど、なにせまだエンジンが・・・。」
結局、カムカバーを開いて、カムタイミングを調整しただけに過ぎないエンジンを騙し騙し回しながら、秋の鈴鹿に出掛ける事になった霞であった。
たった一人、しかも美人の運転するモカブラウンのS600・・・・。
その日、鈴鹿サーキットは、秋田からはるばる自走して来た、霞とそのS600が注目の的となった。
初日のパーティの席で霞はステージに引っ張り出されてしまう・・・。
「このへんで、うちら男連中ですら、びっくり仰天、はるばる秋田から来てくれはった秋山さんにお話を聞いてみたいと思いまんねん・・・。」
「いったい、何時間くらいかかりましたか・・・?」
「すみません、時間ではチョット・・・・・・・・。」
「・・・と言いますと・・・?」
「二日かかって来たんです・・・。」
「ウワーッ!」
一同、大感激のパーティ会場であった。
翌日、少し早めに目の覚めた霞は、洗顔の後、いつものようにシャネルのファンデーションを、ほんの少しだけその白い頬にのせ、明るめのチークとマスカラを使ったあと、パウダーで丁寧に押える。
ほとんど素顔と言っても良いくらいの控え目なメークを済ませると、この日のために用意した深紅のレーシングスーツに、そのしなやかな体を包む。
コミネのジェットタイプの白いヘルメットを手に持つと、まだ朝靄に包まれているパーキングに歩き出す。
兄の形見のそのヘルメット、フェルトの裏側に兄洋一の小さな写真を入れる事を忘れてはいない・・・。
「お兄ちゃん! ついに来たわよ・・、お兄ちゃんが憧れていたサーキット・・・」
霞が東京に出て間もない頃、大学の卒業を控えていた洋一が、ふと、こんな事を話した事があった。
「俺、いつかF−1グランプリをやろうと思う・・・・。」
「なあに、それ・・・。」
「ほら、これだよ!」
こう言って霞の前に広げた外国のモータースポーツの雑誌には、真っ白な葉巻型のレーシングカーが写っていた。 大きな日の丸を描いたそのマシンの美しさと、英語でぎっしりと書き込まれたその記事の中に、太くて大きなHONDAの文字が誇らしげに並んでいた。
 100台ほどのS600とS800が並んだピット前のスペースに、スペアタイヤをはじめ、工具等の重いものを全て降ろし、ホイルキャップを外した霞のS600は、眩しい程に輝いていた。 100台ほどのS600とS800が並んだピット前のスペースに、スペアタイヤをはじめ、工具等の重いものを全て降ろし、ホイルキャップを外した霞のS600は、眩しい程に輝いていた。
一台ずつピットロードから飛び出していくホンダスポーツの集団・・・・。
甲高いエクゾーストノートを残して朝のサーキットに消えていく・・・・。
襟に巻いていたシルクのスカーフを、鼻の上まで引上げて、ヘルメットの顎紐をきつく閉める。
真っ赤なドライビンググローブを着けてファスナーを止めると、手慣れた動作で一速へのシフトを済ませ、オフィシャルの指示を待つ・・・・。
ヘルメットを被る事により、随分、音が静かに感じる。むしろ自分自身の心臓の鼓動が聞こえてくるような気がする程である。
予定通り、三周のパレード走行を終えたその集団は、一旦ピット前に整列したあと、ナンバー付のノーマル車からスポーツ走行に移る。
いくらか下りになっているピットロードを、勢いよく加速して第一コーナーに向かう霞のS600。。
インベタで第一コーナーを抜けたあとは、3速にシフトしたままS字に向かう。
やがてレブカウンターの針が、博士の指示した7000に近づく。
S字の切り返しの辺りで4速にシフトアップしてみるものの、トルク不足ですぐにスピードが落ち始める。
仕方なく3速、7000回転のままで、続く逆バンクまで我慢する。
ダンロップブリッジを抜け、左カーブの180Rにはいった所で、ようやく4速にいれてひとやすみ・・・・。
そして間もなくデグナーカーブ、ヘアピンカーブへと続いていく・・・。
ヘアピンカーブの手前で思いきり右に寄せてフルブレーキング、クリッピングポイントを目掛けて目一杯アクセルを開けると、大きくロールしながらズルズルと外側へ流れ始める。
アンダーステアの状態からアクセルをほんの少しだけ戻してやると、うまい具合にインに向かってフロントが切り込んでいってくれる。
クリッピングポイントを過ぎた所で、思いきり外に逃げながらアクセルを開ける。
きつい上りになっているこのコーナーは、またしてもギヤ比が合わず、シフトアップするとすぐにトルク不足になってしまう。
スプーンカーブに向かうアプローチは、快調にスピードを乗せる事が出来、時速120kmでその複合コーナーに飛び込む。
最初のコーナー手前で3速に押し込み、クリッピングポイントを、多少余裕を持たせてパスし、やがてコース外側ギリギリまで車を運ぶ・・・・。
二つ目のクリッピングポイントを幾分奥のほうにとった霞は、少しだけ右にカウンターをあてながら目一杯アクセルを踏み込む・・・・。
裏のストレートに入ると、例によって、あっという間に4速7000回転に達してしまい、踏み込んでいた右足の力を抜き、アクセルを戻す霞であった。
130Rは無理せず余裕を持って通過した霞は、ピットインの為に右に寄り始めた先行車を左からパスしてシケインに飛び込む。
手早く切り返しを済ませたあと、大きなうねりを感じさせる下りの最終コーナーへと、そのマシンを進める・・・・。
一周6km弱のフルコースを、10周ほどしたところで、予定通りレーシングマシンがコースに入り、混走となる。
案の定、ピットロードから、すさまじい排気音を響かせて飛び出して来る、派手なカラーリングのマシンたち・・・。
S字を抜けた所で、左側をゆっくりと追い抜いてゆく純白のレーシング・・・。
濃紺のストライプは、クラブの会長谷村のマシンであった。
ゆっくりと追い越しながら、右手を上げて合図をしていった彼のマシンを見送るとき、センターに突き出た2本のマフラーから掃き出される排気を見ながら、兄の後ろ姿を見たような気がした霞であった。
バックミラーに注意をしながら、マイペースで走り続ける霞のS600・・・。
一時間程経った頃、フロントガラスに小さな雨粒があたり始める。
見る見る強くなっていく雨足を感じながら、何か嫌な予感がする霞であった。
コースが、すっかり雨に濡れた頃・・・。
S字コーナーの登りで外側から勢い良く追い越して行ったレーシングマシンが、かなり不安定な走りで霞の前に出た。
幅広のスリックタイヤでの濡れた登りコーナーは、テクニックの無いドライバーにとってはスケートリンクと同じであった。
あっという間にリアが滑り出し、オーバーステアからたてなおす間もなくスピン・・。
幸いガードレール手前で止まったそのマシンのドライバーは、まだステアリングを持ったまま硬直している。
雪の路面でのスピンを、嫌という程経験している霞は、この程度の事では動揺する事は無かった。
案の定、スリックタイヤを履いているレーシングマシンは、おしなべてスローダウンして走らざるをえなくなった様である。
ヘアピンカーブの手前で、一台のレーシングマシンに追い付いてしまった霞は、無理をせずにその後ろについて走る事ににする。
と、バックミラーで霞のマシンを見つけたとたんに、そのグリーンのレーシングマシンは、再びスピードを上げ始めたのである。
派手にテールを振り回しながらヘアピンを抜けたそのマシンは、かなり無理な姿勢で続く200Rに飛び込んで行った。
あっという間に30m程にその差が開いたと思った瞬間、 一瞬のアクセルワークの乱れから、行きなり左にテールが流れたそのマシンは、コントロールを失って、右のダートへ勢いよく飛び出して行く・・・・。
雪の上でのそれを、はるかに上回る激しいアクションで飛び出したマシンは、180度回ってこちらにフロントを向け、そのままガードレールに突っ込んで行った。
早めにブレーキを踏んでいた霞ではあったが、これが雪道であったならば、間違いなく跳ね返って、コースに飛び込んで来るくらいの、激しいアクシデントに、思わず膝が震えていた。
左側の路肩ぎりぎりまで逃げた霞のマシンは、辛うじてそのクラッシュシーンに巻き込まれずに済んだものの、さすがに、背筋に冷たいものを感じない訳には行かなかった。
次の周回でそのコーナーを通過したとき、リアエンドを大破したそのマシンの傍で、さみしそうにガードレールにもたれ掛かっていたそのドライバーは、霞のマシンに気が付くと、軽く手を上げて照れ臭そうに笑いかけていた。
「無事でよかったわ・・・。」
幾分気を取り戻してピットに戻った霞であった。
博士の事務所で設立が決まった<F−1放映推進委員会>は、思ったよりも早く、わずか3日でスポンサー26社を集めてしまったのであった。
一人で5社という目標をメンバー全員が達成したのである。それに加えて霞の会社ウェーブカンパニーが通常の電波料の他に、一口加わったのである。
その数日後、霞の発案で、ホンダのディーラーの集まりである<秋田県ホンダ販売店協会>の会長、秋明ホンダ株式会社の猪田社長を訪ねる事になった。
「始めまして、秋山です。」
「テレビ秋田の相田です。」
「よくいらっしゃいました、猪田です。」
「早速ですが、猪田社長!、電話で簡単にご説明した件ですが・・・。ここにおられる秋山先生が会長になってF−1放映推進委員会という会を作られたんです。 そしてお仲間内だけで26社のスポンサーを集めて、F−1を放映して若者たちを喜ばせてあげよう・・・。という事になったのです。」
「そいつはすごい・・・。!」
「とは言うものの、16戦全部を放映する為にはまだまだスポンサーが不足しておるんです。そこでこうしてホンダの関連企業の皆様にも、ご協力頂けないものかと伺った次第です。なんせF−1となるとほとんどホンダのプロモーションビデオを見ているようなものですから・・・・。」
「そりゃそうだ! まさかトヨタさんや日産さんがCM出す訳がないしねー!。」
「解りました、そう云うお話でしたら、是非とも協力させて貰います!。」
「本当に宜しいんですか?」
霞が初めて笑顔を見せた。
「しかし、よくここ迄まとめられましたねー。 我々も本来ならば全面的にスポンサードしたかった所だったのです。 ところが、御存じのようにホンダが連戦連勝の状態でしょう。 ああなるとかえってホンダのCMばかりが並ぶと嫌味になってしまい、逆効果だという事で考えあぐねていた所だったのですよ。 民間のグループがこうして表に出てくれると、我々としてはそれをバックアップする事で、かえってイメージアップになりますから大助かりです。」
「そうおっしゃって頂けるとうれしいです・・・。」
「御礼を言わなければならないのは、我々の方ですよ。 こうなったら本社の方にも全面的に協力させますから任せておいて下さい・・・。」
こうして、霞率いるF−1放映推進委員会と、ホンダ販売店のグループによる二頭立ての協力により、全国でキー局を除けばただ一局、テレビ秋田がF−1グランプリ全戦放映を実現したのであった。
その年、おおかたの予想通り、ネルソン・ピケ、と、ナイジェル・マンセルを起用しているウィリアムズ・ホンダが、その圧倒的な強さを見せつけながら、そのシーズンは始まった。
また、キャメルイエローのロータス・ホンダも、アクティブサスという秘密兵器を投入し、天才セナのドライビングと、日本人初のF−1ドライバー、中嶋悟等の話題が重なって、巷の人気を集めていった。
一週間の予定で入院した霞のS600は、思ったよりも手間取って、二週間を過ぎようとしてもまだエンジンがバラバラのままであった。
「霞さん、ごめん・・・、もう少しだけ待ってくれる?・・・。バラして見たらカムチェーンもいくらか伸びているみたいなので、今、取り寄せているから・・・・。」
「多分そうなるだろうと覚悟はしていました・・・・。」
「でも、来週迄には絶対上げますから・・・・。」
「解っています、その代わり、間違いなく9000回転迄回るエンジンに仕上げて下さいね・・・。」
「大丈夫、保証します!」
その三日後、霞は六本木の飯倉スタジオにいた。
「ハイ、キャロル! スマイルプリーズ」
「OK! NEXTはレフトターンね。」
「OK! GOOD! アイ キャメラね、そうそう良いぞ!」
「ちょっとチンアップ オーライ! オーライ!」
こんな訳の解らない言葉が飛び交う、節目節目に、鋭く響き渡る、ハッセルのシャッター音。
小さなうなり音を発しながら、ストロボがリズミカルにその輝きを繰り返す。
「OK! ジ・エンド!」
「お疲れ様でした・・・・!」
手早く道具を片付けると、同じビルの三階にあるレストラン<ア・タント>にむかう。
AXISと呼ばれるそのビルは、同名のデザイン誌まで発行していて、デザイナーの溜り場のようになっていた。
「やあ!・・・」
中庭を見下ろす形になっている、テラスのテーブルに座っていた沢木が、右手を上げて合図をする・・・。
「お待たせしてすみません。」
「いや、僕の方こそ無理に押し掛けてきちゃって。」
「先生、何だかとってもお元気そう。」
「やっぱりそう思いますか?。」
「何か良い事がおありになったんですね・・・。」
「そう! とっても良い事がありましてね・・・。」
そうやってうれしそうに答える沢木を<何て無邪気な人なんだろう・・>と感じる霞であった。
「あてて見ましょうか?」
「うん・・・」
「ゴルフのコンペで優勝した!。」
「ブーー、・・・大外れ!。」
「じゃあ、飼っている猫が子供を産んだ・・・。」
「ブーー、・・・残念でした、うちの猫は雄でした。」
「何かしら・・・・?」
「もっと良い事・・・・。」
「恋人・・・・?。」
「あ・た・り。! 実は素敵な恋人が出来たんですよ。」
「うわーっ、素敵! 先生のようなお洒落な方の恋人って、きっと綺麗な方なんでしょうね。」
「ええ、ちょっとその辺にはいない美人です・・・。」
「まあ、ごちそう様です・・・。」
「女房と別れて十年になりますが、もう二度と結婚なんて・・・、と思っていたのが、ころりと気が変ってしまいましたから・・・。いい年をして困ったものです。」
「いい年だなんて、とんでもありません、先生とっても素敵だから恋が似合っています。
本当に・・・・。」
「ありがとう! 霞さんにそう言われると元気百倍です・・・。」
「それはそうと、今日はもう良いんでしょう・・・。」
「ええ。」
「それでは、ゆっくりと再会を祝って乾杯、といきましょう。」
そう言うとテーブルの上のワイングラスを持ち上げて、その美しい液体に霞の笑顔を透かして見つめる。
「先生のオリーブグリーンのジャガーと、素敵な恋にかんぱーい。」
「そして霞さんのS600にも・・・。」
その日、約束どおり沢木は、表参道にある自分の仕事場へ霞を案内した。
夜9時を回ったというのに、その仕事場の中は、多くの若者たちでごった返していた。
ドラフターに向かって、何やら真剣に考え込んでいる者。
発泡スチロールの白いボードを切り取って模型を作っている者。
木や石のサンプルを持って、話し合っているグループ。
みんなそれぞれ活き活きと動き回っていた。
一通りの見学が終ると、沢木のディスクのある部屋に入った。
吹き抜けに面した壁が、大きなガラスになっていて、若者たちの仕事部屋からもよく見えるその部屋は、静かな落ち着いた空間であった。
その夜霞は、自分の知らない世界、超一流の建築家の仕事の世界を、垣間見たのであった。
アラブの王様から依頼された、都市一つを、そっくり作り替える為のプロジェクトの、ベーシックプランの事や。 北海道の草原の、ど真ん中に造るコンサートホールの事などなど・・・。
そして、プライベートな事もほんの少しだけ・・・・。
10年前に離婚をされていて、たった一人のご子息は大学を出たあと、ロンドンの専門学校に留学中の事・・・・。
広尾のマンションに独り住いで、ガウディという名前の雑種の雄猫を一匹飼っていて、仕事が行き詰まった時などは、大声でその猫を叱りつけて気分転換をする事・・・・。等など・・・。
今や建築雑誌のみならず、ファッション誌や、週刊誌に至る迄、毎週のように顔を出している、超売れっ子の建築家の表の顔とはまた違った、何処か桁外れの人間臭さも持ち合わせている沢木に、憧れとは違った、心の真底が暖まるような、不思議な感情を持ち始めている自分に気が付いていた。
翌日、朝一便で秋田に帰った霞は、空港のパーキングに止めておいたS600クーペに乗って、まっすぐに山の上の自分の部屋に向かう。
飛行機が予定通りに着いたので、一旦部屋に戻ってシャワーを使うことが出来た。
いつもの様にシャワーの後は、野菜ジュースで朝食をとりながら、留守番電話のメッセージのスイッチを押す。
「ピー ; 霞! 俺、雄二。今、夜の9時。 明日の夜、会いたい・・・。 いつものところで待っているから、もし都合が悪ければ昼のうちに連絡を頼む。 じゃあ・・・」
根岸雄二、霞の中学のクラスメートで、10年程前からは霞の恋人として、そして何でも相談出来る、頼れる友人として、付き合っている男である。
国会議員、根岸満治郎を父に持つ雄二は、今は家業の薬問屋を父に代わって切り回しているが、いずれは父の跡をついで自民党の派閥の石の一つになる運命になる事を、誰よりもよく解った上で、自分の将来を見据えていた。
その夜、仕事を終えた霞は、フランス製のシルクのショーツとブラを着け、買ったばかりのヨージ・ヤマモトのパンツスーツに身を包むと、トレンチコートを手にしてタクシーを拾う。
久し振りに訪れたその部屋は、雄二が、霞と逢う為だけに買い求めたマンションであった。
ひと月ぶりに逢った霞を、何も言わずに抱き締める雄二の腕のぬくもりに、何か、いつもと違うものを感じた霞であった。
「ビール飲む?・・・、それともワイン?」
そう言って霞の耳元でささやくくせに、抱き締めている腕は、いっこうに放そうとはしていない・・・。
「ううん、何にも要らない、このままこうしていて・・・・。」
再び強く唇を求めてくる雄二の激しさに、やがて小さく膝が震えて、雄二の背中に回した手に、そして指に思わず力が加わる霞であった。
「霞!・・・」
耳元で雄二の声がする。
雄二の胸の中に顔を沈めて、眠っていた霞は、その声で目が覚めたものの、動くのをためらっていた。
「なあ・・・・、どうしても駄目か?」
「うん・・・」
「どうしても?」
「うん、どうしても・・・・」
「おまえ、やっぱりどうかしているぜ!」
「分かってる・・・、ふつうの女になれなくてゴメンネ・・・・」
「考えてみろよ、俺と結婚すりゃ、ゆくゆくは代議士夫人だぜ、金だって無い訳じゃないし、男前だってそれは上の上とはいかないけど、平均レベルはクリアしてるだろ。 もちろん、身体だってこのとおり丈夫だし・・・、それよりも何よりも、霞が大好きで他の誰にも・・・・」
「分かってる、雄二がどんなに私を大切に想ってくれているか・・・。 雄二みたいに素敵な人、そんなにざらにいないって事も十分解ってる・・・。 でも・・、私、結婚しない。 誰とも・・・・。」
「でも、もう10年だぜ。 いつまでもこのままって云うのは、世間がほっといてくれないんだよ、いつまでも独身で通す訳にもいかないんだよな・・・俺の場合は・・・・。」
「ごめんね・・・雄二・・・。」
「そんなに仕事が楽しいのか・・・?」
「楽しいとか云う問題じゃなくって、もっと違った私の・・・・」
「何度も聞き飽きたよ! 結婚と云うルールに縛られたくないんだろ、恋は恋、仕事は仕事、何も家庭に入るだけが女の幸せじゃない・・・・。って云うんだろ。」
「雄二の事、尊敬してるし、男としてもとっても魅力を感じている・・・。でも、結婚に対する観念的なものは、私とは別の世界にいる人だと思うの。 雄二は私みたいな女からは離れて行く時がくるわ・・・・、きっと・・・。」
「そんな事はない!、お前の考え方、解らない訳じゃないし、それを嫌だとも思わない。でも俺の立場、特に政治家を目指す俺には、それを許して貰える環境がないんだ。」
「俺、 見合いをするかもしれない・・・・。実は、東部銀行の頭取の娘との話があるんだ。もちろん断わるつもりだけど、霞がいつまでも俺のプロポーズを受けてくれないとなると、いつかは別れなければならなくなるかも・・・・。」
「頼むから、俺の女房になってくれよ!・・・」
じっと押しつけていた雄二の胸から、ようやく頬を離して顔を上げた霞の瞳には、たっぷりと透明な液体が溢れ、長いまつ毛を伝わって、大粒の涙がとめどなくこぼれ落ちていた。
その夜、雄二に恋の終わりを告げ、大切に隠し持ってきたその部屋のキーを彼の掌に返した霞は、二度と振り返らないで夜の歩道を歩き始めた。
<雄二! ごめんなさい・・・・>
涙にぼんやりかすんで見える星空に向かってこんなフレーズを口ずさむ・・・。
Everything must change,
Nothing stay`s the same.
Every one must change,
No`one stay`s the same.・・・・・

タクシーを拾って、山の上の自分の部屋に戻った霞は、まだ雄二の手のぬくもりの残っている、火照った身体を、ぬるめのシャワーで鎮める。
時計を見ると、もうすでに12時を過ぎているが、とても眠る気にはなれない・・・。
思いたって、今度はジーンズを履くと、S600クーペに乗り、再び深夜の闇の中に飛び出して行った。
いつも霞が、夜のドライブコースとして使っている空港迄の道は、深夜は全くと言っても云い程車が通らない。 片道30km程のそのコースを、ほとんど100km/h以上の速度で走り続け、あっと云う間に丘の上にある、その空港の前に車を止める。
水銀灯に映し出されたその駐車場も、ライトが点滅する塔も、いつの間にか涙に覆われて、ぼんやりとそのシルエットを崩していく・・・・。
「ごめんなさい・・・・」
誰に言う訳でもなく、そんな謝りの言葉を口に出すと・・、とめどなく頬を伝う涙が、トレーナーの胸元を濡らしていく・・・。
30分程、独りっきりで泣き続け、すっかりと泣き疲れた頃。
「霞、あんまり無理するなよ・・・。」
兄、洋一が、何処からともなく声をかけてくれる。
「お兄ちゃん・・・・」
一瞬、父親がわりだった洋一の姿を見た霞は、甘えん坊だった、子供の頃の自分に戻っていた。
時計を見ると、もう1時になろうとしていた。
「先生・・・・」
「まだ起きていますか・・・・・?」
兄の面影の上に、沢木の優しく澄んだ瞳が重なり、急に子供のようなわがままをしてみたくなった霞は、ロビー前の電話ボックスの前まで車を進める。
100円玉を数個手に持つと、教えられていた通り、沢木の自宅の番号を一つずつ、ゆっくりと押す・・。
三回程コール音がした後、低くて聞き覚えのある声がする。
「はい、沢木です。」
「ワーイ、先生!起きていたー。」
「誰・・・?」
「こんな夜中に電話をする、困った私は誰でしょうか・・・?」
わざと明るくはしゃぐ霞の声に、すぐ気がついて・・・。
「霞・・・さん・・?」
「ピポ・ピポ・ピポーン、当たりでーす!。」
「どうしたの、・・・酔っているの?・・・」
「ごめんなさい・・・、こんなに遅く電話しちゃって・・・、怒って下さい!。」
「いや、! 全然迷惑じゃない。 さっき帰ったところだから構わないけど・・・。」
数秒間の沈黙のあと・・・・。
「何かあったんですね・・・・・。」
「うぅん、・・・何も・・・。」
沢木の優しい言葉を聞いたとたん、また再び、涙があふれ出てしまう・・・・。
「何か・・・、なにか話して・・・・。」
霞の涙声にびっくりした沢木は、一瞬言葉に詰まる・・・。
「先生・・・!、 逢いたい・・・・・。」
無理と知りながら、子供のようなおねだりをする霞であった。
そして、その涙声に、沢木も堪え切れない何かを感じていた。
「霞さん、今、何処にいるの?・・・」
「秋田の空港・・・・・、 先生・・・逢いたい・・・・・!」
「わかった! すぐに行く! これからすぐに・・・・。」
「朝、 そうだ、朝陽が昇る頃、田沢湖で逢おう・・・・、 この間別れた駐車場で・・・・。 きっとだ!・・・良いね・・・・。」
「・・・・・・・。」
それから数時間後。
真っ暗なベールをまとった湖のホテルの駐車場に、霞のS600クーペは湖に向かってその銀色のボディを静かに休めていた。
時々ヘッドライトを湖面に向けて点灯させてみる。
鏡のように静まりかえっている湖面・・・。
ライトの光りに照らし出される瞬間に、小さく身震いをするように光って見える。
やがて、山の向こうから、闇の呪文が解けていくように明らみ始める。
そして、もうすぐ訪れる朝の営みが・・・・・。
広尾の自宅から、この湖までは、少なくとも500km以上はあるはずだから、まさかこんなに早く表われる筈はないと思いながらも・・・・。
<もうすぐあの湖の向こう岸に沢木のジャガーのライトが輝いて、霞の元まで飛んで来るはず・・・・、そう、もうすぐに・・・・。>
そんな事を信じて、じっと湖をみつめながらたたずむ霞であった。
しかし電話を切ってから、まだ三時間半しか経っていないのである・・・・。
「お願い、まだ朝にはならないで・・・。」
<朝陽が昇る頃・・・・>、確かにそう言った沢木の約束・・・・。
絶対に無理だとは知りながら、沢木が魔法を使って飛んで来るような気がして、じっと待つ霞である。
と、対岸にキラリと光るものが見える。
湖の縁を縫うように動くその星のような瞬きは、あっという間に霞のいる駐車場に近づいて来る。
やがて、タイヤのきしむ音や、太く吠えるようなそのエクゾーストノートまでが、霞の耳まで届くようになり、本当にあっという間に、霞の前にその美しい姿を現したのであった。
沢木は、S600の隣りにジャガーを横付けると、立ちすくんでいる霞に向かって言った。
「おはよう!、霞おじょうさま・・・・。」
「先生・・・・!」
くしゃくしゃに崩れた笑顔で、沢木の胸に飛び込み、しがみつく霞・・・
<本当に可愛い人だ・・・>。
駄々っ子のような霞を抱き締めて、こう感じた沢木であった。
「間にあったでしょう・・・・、朝日が昇る時に・・・・。」
「先生すごい・・・、魔法を使ったんでしょう・・・・。」
「ちょっとだけ・・・・ね。」
「うれしい・・・・!」
「先生、ごめんなさい・・・、本当にごめんなさい・・・・。」
「久し振りに無茶をしてしまった・・・・。」
「本当に、とんでもないやつだ! この娘は・・・。」
「だって・・・・。」
父親の胸も、背中も知らない霞であったが、沢木の胸に抱かれている時に、兄とも、そして雄二とも違った、まるで父の胸に抱かれているような、居心地のよいものを感じたのであった。
「今度お呼びになる時は、もう少し時間の余裕を頂ければ助かります・・・、霞おじょうさま・・・。」
「分かりました!、 心しておきます・・・・。」
その朝、沢木のジャガーに乗り、湖の回りを何度も回りながら陽の昇るのを見た二人はホテルのレストランで朝食を食べたあと、再び沢木は東京へ、霞は秋田市に向かって戻って行った。
もうそこには、駄々っ子の霞はいなかった。
またひとつ、たくましさを増した美しいレディが、更にその輝きを増して育って行ったのであった。
つづく・・・
目次へ戻る
次の章へ
|